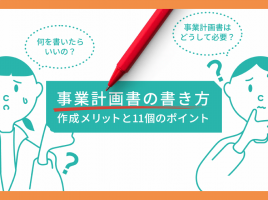接骨院・鍼灸院で療養費施術を行う際に注意すべきこと
業界全体の適正化の流れにより、療養費の取り扱いが以前より厳しい状況になっています。とは言え、患者さまの金銭的負担を考えると、なかなか自費施術への移行に踏み切れない方も多いのではないでしょうか。療養費を正しく取り扱うために注意すべき項目、そして、これから接骨院・鍼灸院を経営していく上での施術メニューの展開についてお話したいと思います。
目次
1.接骨院、鍼灸院の療養費を取り巻く現状

まずはじめに、接骨院、鍼灸院の療養費を取り巻く現状についてお話します。
1-1 柔道整復療養費額は減少の一途を辿っている
1-2 院や鍼灸接骨院は増加している
1-3 療養費に関する制度変更
1-4 療養費が適用される症状とは
1-1 柔道整復療養費額は減少の一途を辿っている

柔道整復の年間療養費額をご存知でしょうか。2011年には4,000億円を超えていましたが、2012年頃を境に減少の一途を辿り、2017年には3,437億円にまで下がりました。要因としては、療養費給付の監査が厳しくなったことによる回答書の増加、適正な療養費請求が増えた、療養費を取り扱う施術所が減少した、書類不備などによる保険者からの返戻が増加した…などの様々な理由があります。
その一方で、2018年度の国民医療費は43兆3,949億円、前年度の43兆710億円に比べ3,239億円上回り、0.8%の増加となっています。高齢者人口が年々増加すると共に、医療費も並行して増額傾向にあります。
1-2 接骨院や鍼灸院は増加している
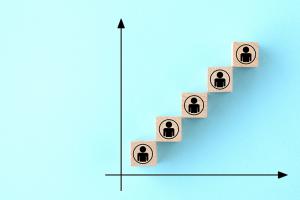
鍼灸やあん摩・マッサージ指圧の療養費額が前年と比べてあまり変化がないにもかかわらず、なぜ柔道整復療養費は減少傾向にあるのでしょうか。その要因のひとつに、給付における監査が厳しくなったことがあります。そんな状況下でも柔道整復師を目指す人は増え、2008年は約4.3万人でしたが、2018年には約7.3万人と、2倍近くにまで登りました。施術者が増加したことにより、不正請求への監査をさらに強化し、適正な療養費申請に対してのみ給付を行えるよう、以前よりも厳しく取り締まりを行っているのです。それ故、療養費請求を行っても、受け取る療養費が増えるとは考えづらい状況だと言えます。
1-3 療養費に関する制度変更

柔道整復などにまつわる制度は、度々改正されています。直近だと、2019年1月より、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者が患者に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の受領委任制度が柔道整復の場合と大きく異なる点は、「受領委任に参加するかどうかは保険者ごとで個別に決める」ということです。保険者が受領委任に参加しないと決めた場合、償還払いや委任払いなど、その保険者がこれまで行っていた取扱いを継続する形になります。はりきゅうの療養費支給申請には、保険医の同意書または診断書が必要です。
1-4 療養費が適用される症状とは

厚生労働省では、「接骨院や整骨院において『骨折、脱臼、打撲および捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)』の施術において療養費の対象になる」と定められています。慢性的な肩こりや腰痛の施術には療養費は適用されず、全額患者さまの自己負担となるため、事前の説明が必要です。療養費を取り扱う際は、適用できる症状なのか、できない症状なのかをきちんと明確化する必要があります。そのためには、患者さまへのヒアリングの際、しっかりと情報共有を行っておきましょう。
療養費施術をする際の患者さまの一部負担金(窓口で支払うお金)は、原則3割とされています。一部負担金の割合は、患者さまの年齢や所得額などにより変動するため、療養費施術を行う際には必ず確認しましょう。
参考:厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」
2.療養費請求で注意すべき点

次に、療養費請求をする上で注意が必要な点について見ていきたいと思います。
2-1 療養費支給申請書の返戻
2-2 療養費の不正請求
2-3 施術の根拠を示す「施術録」
2-4 事実を調査するための「回答書」
2-5 療養費に頼り過ぎの接骨院経営
2-1 療養費支給申請書の返戻

療養費施術を行っている場合、保険者へ療養費支給申請書(通称「レセプト」)を提出する必要があります。提出した療養費支給申請書は、審査支払期間と保険者によって細かくチェックを行います。請求内容に不備がある時に療養費支給申請書は差し戻しされます。このことを「返戻」と呼びます。
療養費支給申請書が返戻になる理由としては、項目に不備や不明点があった場合などが挙げられます。具体的には、資格喪失や番号・記号の記載ミス、症状に対して行った施術内容が一致していない、誤った診療報酬点数を入力されている…などがあります。返戻になった療養費支給申請書は、指摘された項目を正確に修正し、再提出をする必要があります。再提出の際は、返戻付箋がついた療養費支給申請書に二重線で訂正し、訂正印を押印して再請求することが求められます。保険者によっては「新しい療養費支給申請書と、返戻付箋が付いた療養費支給申請を提出してください」と言われる場合もあります。
登録すると続きをお読みいただけます。
既に会員登録をお済ませいただいている方は、
ログインページよりログインしてお進みくださいませ。
アクセスランキング
-
1
 柔整師・鍼灸師の施術メソッド
柔整師・鍼灸師の施術メソッド -
2
 柔整師・鍼灸師の施術メソッド
柔整師・鍼灸師の施術メソッド -
3
 柔整師・鍼灸師の施術メソッド
柔整師・鍼灸師の施術メソッド -
4
 柔整師・鍼灸師の施術メソッド
柔整師・鍼灸師の施術メソッド -
5
 柔整師・鍼灸師の施術メソッド
柔整師・鍼灸師の施術メソッド
関連記事
-
 正しい療養費請求
正しい療養費請求 -
 正しい療養費請求
正しい療養費請求 -
 正しい療養費請求
正しい療養費請求
関連記事
-
 2021.07.16柔道整復の療養費制度~償還払いと受領委任~多くの接骨院で取り扱われている受領委任制度ですが、受領委任の理解度については少し不安に思っている方も少なくないのではないでしょうか。原則、療養費は償還払いであるのに接骨院で受領委任が適用されるのはなぜか、受領委任のメリット・デメリットは何か。今回は、療養費制度の要である受領委任について詳しくわかりやすく解説します。
2021.07.16柔道整復の療養費制度~償還払いと受領委任~多くの接骨院で取り扱われている受領委任制度ですが、受領委任の理解度については少し不安に思っている方も少なくないのではないでしょうか。原則、療養費は償還払いであるのに接骨院で受領委任が適用されるのはなぜか、受領委任のメリット・デメリットは何か。今回は、療養費制度の要である受領委任について詳しくわかりやすく解説します。 -
 2021.07.27療養費支給申請書の「返戻」とは療養費請求において避けては通れないのが「返戻」です。返戻とは、保険者(または請求団体)に提出した療養費支給申請に何らかの不備・疑義があり返却されることです。なかには療養費支給申請書が返却されず「不支給」と判断される場合もあります。返戻と不支給はどちらも療養費が支給されない状態ですが、返戻の場合、修正すれば再提出が可能となります。本コラムでは、返戻と不支給の違い、それぞれの対処方法について解説します。
2021.07.27療養費支給申請書の「返戻」とは療養費請求において避けては通れないのが「返戻」です。返戻とは、保険者(または請求団体)に提出した療養費支給申請に何らかの不備・疑義があり返却されることです。なかには療養費支給申請書が返却されず「不支給」と判断される場合もあります。返戻と不支給はどちらも療養費が支給されない状態ですが、返戻の場合、修正すれば再提出が可能となります。本コラムでは、返戻と不支給の違い、それぞれの対処方法について解説します。 -
 2021.11.11間違えやすい窓口負担金の認識鍼灸院や接骨院の窓口負担金は、基本的には過不足のない料金をいただくことがルールとなっています。算定基準に該当しない追加料金または割引を行うことはできません。 本コラムでは、柔道整復・鍼灸の窓口負担金の違い、自費施術との併用した場合の考え方について解説します。
2021.11.11間違えやすい窓口負担金の認識鍼灸院や接骨院の窓口負担金は、基本的には過不足のない料金をいただくことがルールとなっています。算定基準に該当しない追加料金または割引を行うことはできません。 本コラムでは、柔道整復・鍼灸の窓口負担金の違い、自費施術との併用した場合の考え方について解説します。

-
 法令など業界の
法令など業界の最新情報をGet! -
 オリジナル動画が
オリジナル動画が
見放題 -
 実務に役立つ資料を
実務に役立つ資料を
ダウンロード